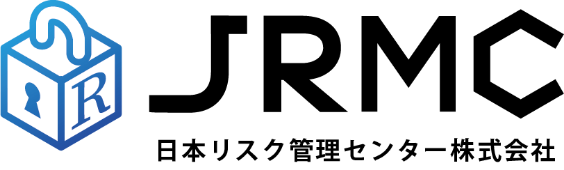お知らせ
SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)と反社会的勢力リスク
目次
近年、SNSの普及により個人や企業が手軽に情報発信を行えるようになりました。しかし、その利便性の裏には様々なリスクが潜んでおり、特に「反社会的勢力(以下、反社)」との関わりは企業にとって致命的な問題となる可能性があります。SNSを活用する際の反社リスクについて解説し企業や個人がどのように対応すべきかを考察します。

反社会的勢力とは何か
まず反社とは何かを明確にする必要があります。反社とは、2007年に公表された「企業の反社会的勢力による被害を防止するための指針」において、「暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人」と定義づけられており、これらは違法な手段で資金を得ることを目的として、企業や個人に対し恐喝・詐欺・マネーロンダリングといった違法行為を行うことが多く、政府や警察庁では企業が反社との関係を持たないよう強く求めており「暴力団排除条例」や「犯罪収益移転防止法」などの法的枠組みも整備されています。これに違反した場合企業の社会的信用は大きく損なわれ場合によっては刑事責任を問われることもあります。
SNSと反社リスクの関係
SNSの発展により企業や個人が発信した情報は瞬時に拡散されるようになりました。その結果、意図せず反社と接点を持ってしまうリスクも高まっています。
1.SNS上での反社の存在
SNS上では反社と一般人や企業が接触するケースが増えています。例えば、反社がビジネス系アカウントを運営し投資話やビジネスチャンスを持ちかけることがあります。特に暗号資産や投資詐欺・ネットワークビジネスを装った勧誘が後を絶たちません。
2.企業の公式アカウントが反社とつながるリスク
企業の公式アカウントがフォロワーやリツイートを通じて反社と関わるケースもあります。たとえば、ある企業の公式アカウントが反社と知らずにその投稿をシェアしたり交流を持ったりすると企業イメージの低下につながります。
3.インフルエンサーとの関係性
企業がSNSマーケティングを行う際にインフルエンサーを起用することが一般的になっていますが、インフルエンサーの過去の言動や交友関係に反社とのつながりがある場合、企業が間接的に反社と関与していると見なされる可能性があります。
4.SNSを通じたクレーム対応
企業アカウントがユーザーからのクレームに対応する際、悪意ある第三者(反社を含む)に絡まれることもあり、誤った対応をすると企業が恐喝や名誉毀損などのトラブルに巻き込まれる危険性があります。
反社リスクを回避するための対策
企業や個人がSNS運用において反社リスクを回避するにはどうすればよいのかについて、以下のような対策が求められます。
1.SNS運用ポリシーの策定
企業はSNS運用に関するガイドラインを明確にし、反社との接触を防ぐ方針を定めるべきです。特にフォローバックやリツイートの基準を明確にすることで不適切なアカウントとの関わりを防げます。
2.インフルエンサーの事前チェック
SNSを利用したマーケティングを行う際にはインフルエンサーの過去の投稿や交友関係を十分に調査することが重要です。企業としてインフルエンサーに関するデュー・ディリジェンス(適正調査)を実施し問題がないか確認すべきです。
3.不審なアカウントとの関係断絶
反社と疑われるアカウントからのフォローやコメントには注意が必要です。もし明らかに怪しいアカウントと接点を持ってしまった場合速やかにブロックや通報を行うことが重要です。
4.社内教育の強化
企業内でSNSのリスクについての教育を徹底し、社員が意識を持って対応できるようにします。特に、SNSを運用する担当者には反社に関する基礎知識を学ばせ対応方法を指導すべきです。
5.法務部門や専門家との連携
SNS運用における法的リスクを最小限に抑えるために法務部門や専門家との連携を強化することも効果的です。特に大手企業ではSNS運用の監査体制を整えることが望ましいと思われます。
まとめ
SNSは現代において欠かせないツールの一つですが、反社リスクをはじめとした様々な危険が潜んでいます。企業や個人はSNS上での交流を慎重に管理し反社との関係を徹底的に排除することが求められます。特に企業アカウントの運用においてはガイドラインの策定・インフルエンサーの適正調査・社員教育の強化・法務部門との連携などを通じてリスク管理を行うことが重要であり、SNSの利便性を最大限に活用しつつ健全な企業活動を維持するためにも反社リスクへの適切な対応が不可欠です。リスク管理においては日本リスク管理センターの反社DB(反社チェック・コンプライアンスチェック)を有効利用することで適切な管理を行う事ができます。

※わかりやすい料金プランでコストを抑えます
※警察独自情報の検索が可能
※個人名・会社名のみで検索可能(ネガティブワードの指定は不要)
※全国紙に加え地方新聞”紙面”の情報を網羅
※最短で即日導入可能