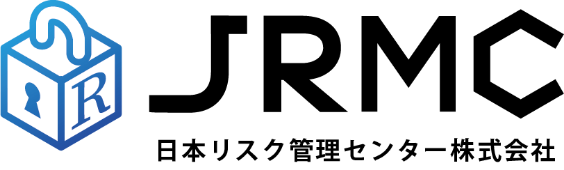お知らせ
「オレオレ詐欺」はなぜなくならないのか?
オレオレ詐欺(振り込め詐欺)に代表される特殊詐欺は依然として日本国内の大きな社会問題となっています。警察の取り締まりが強化され、多くの犯人が逮捕されているにも関わらず被害は後を絶ちません。それどころか手口はますます巧妙化し詐欺の形態も多様化しています。オレオレ詐欺がなくならない理由やその進化、最新の手口について詳しく掘り下げ個人や企業が注意すべきポイントを考察します。
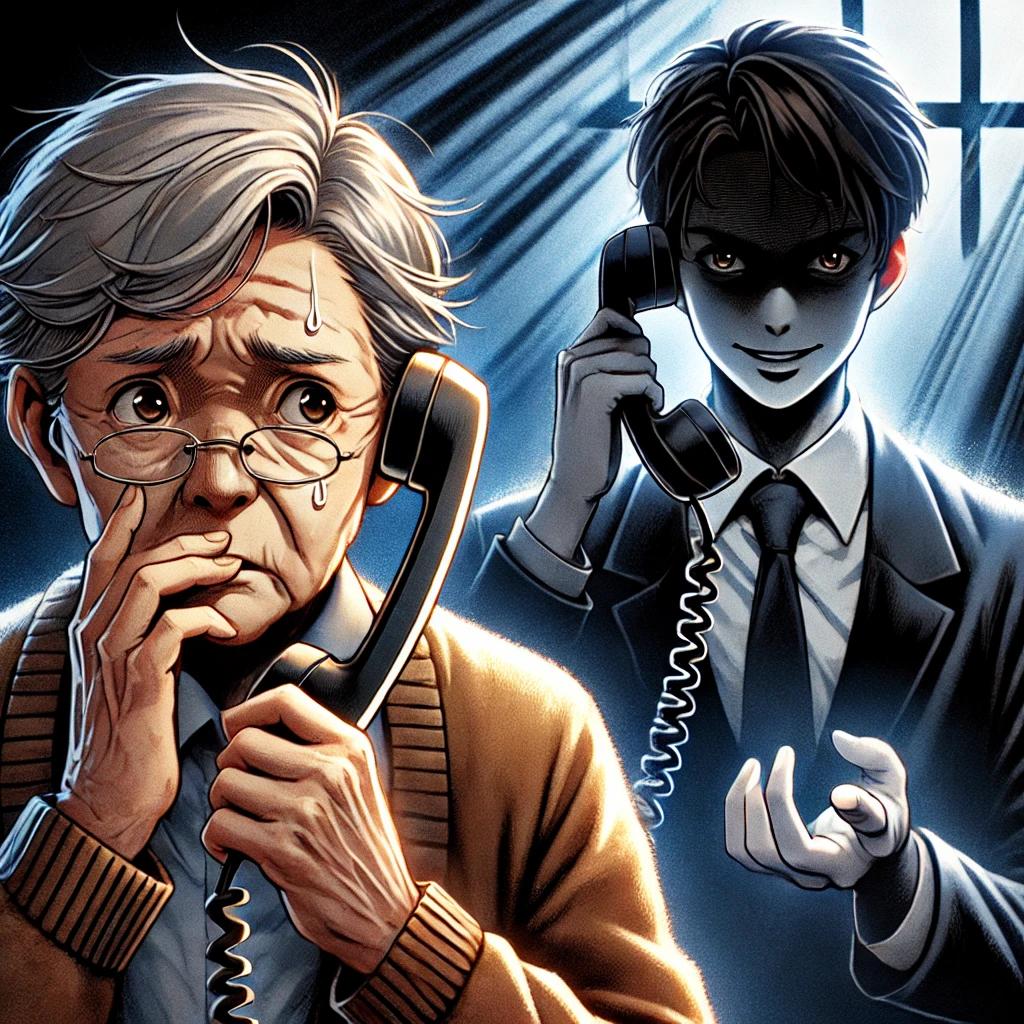
1. オレオレ詐欺の進化と最新の手口
オレオレ詐欺の基本的な手口は、電話などを用いて相手に対面することなく被害者(特に高齢者)をだまし指定の口座に金銭を振り込みさせて直接現金を受け取るものです。しかし近年の詐欺グループは新たな手法を次々に生み出し警察の対策をすり抜けています。
1.1. 従来の手口
● 「オレオレ」型
息子や孫を装い「事故を起こした」「会社の金を使い込んだ」などの理由で金銭を要求。
● 「架空請求」型
未払い料金や税金の督促を装い支払いを迫る。
● 「還付金詐欺」型
役所や保険会社を装い還付金を受け取るためにATMを操作させる。
1.2. 最新の手口
● 「劇場型詐欺」
複数人が関与し警察や弁護士などになりすまして信憑性を高める。
● 「アポ電詐欺」
事前に電話で資産状況を確認し狙いを定めたうえで詐欺を仕掛ける。
● 「デジタル詐欺」
SNSやメールを利用し電子マネーや仮想通貨での支払いを求める手法。
2. 検挙してもオレオレ詐欺が減らない理由
2.1. 組織化された詐欺ビジネス
オレオレ詐欺はもはや個人犯罪ではなく厳密な組織体系のもとで運営されています。主犯格は決して表に出ず、電話をかける役・現金を受け取る役・指示を出す役など、役割が分業され摘発されてもすぐに別のメンバーが補充される仕組みになっています。
2.2. 高額報酬と低リスク
詐欺に関与する若者の中にはSNSや闇バイトで簡単に募集される「受け子」「出し子」から犯罪に手を染めるケースが増えています。数回の犯行で数十万円〜数百万円の報酬が得られるためリスクを負ってでも手を出す人が後を絶ちません。
2.3. 犯行拠点の国外移転
近年ではフィリピンやタイなど海外に拠点を置く詐欺グループが増えています。海外からの電話で詐欺を行えば日本の警察がすぐに逮捕することが難しくなり摘発が遅れることになります。
3. 家族や企業が気をつけるべきこと
オレオレ詐欺の被害を防ぐためには個人だけでなく企業や地域社会が一体となって対策を講じることが必要です。
3.1. 家族の対策
● 合言葉を決める
家族間で緊急時の合言葉を決めておき電話で確認する。
● 高齢者に周知する
定期的に詐欺の手口を説明し知らない番号からの電話には出ないよう指導する。
● 警察・金融機関との連携
不審な電話を受けた場合すぐに警察や銀行に相談するよう促す。
3.2. 企業の対策
● 社員教育を徹底
特に経理担当者には詐欺のリスクについて定期的な研修を実施。
● 二重確認を義務化
大口の送金や取引を行う際には別の担当者による確認を行う。
● セキュリティ強化
サイバー攻撃による情報漏えいが詐欺の引き金となることもあるため情報管理の強化を図る。
3.3. 地域・社会の取り組み
● 防犯ネットワークの構築
町内会や自治体が連携し詐欺の情報を共有する。
● 金融機関との協力
銀行窓口での声かけを強化し不審な取引があれば通報する体制を整備。
● メディアの活用
テレビや新聞・SNSを通じて最新の詐欺手口を広める。
4. まとめ
オレオレ詐欺は日々進化しながら私たちの身近なところで発生しています。取り締まりが強化されても新たな手法が次々に生まれるため被害を完全になくすことは容易ではありません。しかし家族や企業・地域社会が連携し最新の手口を学びながら警戒を続けることで被害を減らすことは可能です。
詐欺の被害に遭わないためには、「電話だけでのやりとりを信用しない」「不審な連絡があれば必ず確認する」「日頃から家族で防犯意識を共有する」といった基本的な対策を徹底することが重要です。私たち一人ひとりが意識を高め詐欺グループの思惑に乗らないよう注意していきましょう。
リスク管理においては日本リスク管理センターの反社DB(反社チェック・コンプライアンスチェック)を有効利用することで適切な管理を行う事ができます。

※わかりやすい料金プランでコストを抑えます
※警察独自情報の検索が可能
※個人名・会社名のみで検索可能(ネガティブワードの指定は不要)
※全国紙に加え地方新聞”紙面”の情報を網羅
※最短で即日導入可能